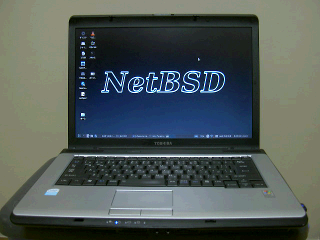NetBSDからFreeBSDのちOpenBSDチラッとMageia結局NetBSDとMageiaをマルチブート
NetBSDからFreeBSDのちOpenBSDチラッとMageia結局NetBSDとMageiaをマルチブート
NetBSDからFreeBSDのちOpenBSDチラッとMageia結局NetBSDとMageiaをマルチブート
XPからNetBSD 6.1.xに入れ替え、7.0までアップグレードしているdynabook、RAMも512MBから2GBに増強、無線LANでも動画視聴も快適になることを確認、わかってはいたものの、消費電力を計測してみたら、やっぱり、日常使うのはノート(dynabook)だよねとDebian/Fedora/NetBSDマルチブート構成のデスクトップマシンからメインをdynabookに切り替え、ラズベリーパイを買ってDLNAサーバやファイルサーバ(NAS)に。
理由はともあれ、どんなOS・ディストロでも他に載せ替えてみちゃおうかなーと思う瞬間があるもので最終的にRaspbianにしたラズベリーパイも当初NetBSDにするつもりでいた、そんなNetBSDも例外ではなく、あまりにいろいろ積み重なると、もうちょっと手のかからないディストロ他にないかな。。。という瞬間が訪れることもあって、今回は、ふと思いを巡らせてみることにした。
結果、FreeBSD、OpenBSDをインストール、試用した後、これならNetBSDの方がよいと判断もMageiaも気になり、MageiaとNetBSDをマルチブートするもマルチメディア関連についてMageiaはLinuxらしからぬ状況でそこだけ見るとNetBSDの方がよい。。。それならということでNetBSDをクリーン(上書き)インストールしてみたが、NetBSDをメインで使うにしてもLinuxもあると何かと融通が利くこともあるし、やっぱりMageiaも入れとくかとマルチブートすべくNetBSDを入れ直しつつ、Mageiaをインストールすることにした話。
ちなみに手元には、既にDebian/Ubuntu/Fedora/CentOS、NetBSD/OpenBSD/FreeBSD、ClonezillaやGParted等々が入ったUSBメモリがあります。
以前、この各種インストーラ兼ディストロLive版兼レスキューUSBメモリスティックを作るにあたり、GPTにした為、基本パーティションの数を気にすることなく、とはいえ、つくりによっては?イメージ書き込みの他、ISOブートやファイル展開による仕込みもできることがわかったので、それほどパーティションを切る必要もなく、新たにディストロのインストーラを入れるにしてもパーティションを切るならddなど、そうでなければ、より手軽な方法を選ぶことができる可能性もあるので気軽にあれこれできます。
ディストロ選び
NetBSDを入れ替える候補といったら、まずは、FreeBSDかOpenBSDでしょう。
ただ、滅多に使わないけどUSB接続のCUPSプリンタはサーバ上にあっても認識してほしい、PCやりながらという意味では、視聴し始めたばかりとはいえ、動画やインターネットラジオ、手持ちのCDをリッピングした音楽ファイル、DLNAサーバにおいてDLNAクライアントとして視聴したい、ついては選択肢が多いに越したことはない。。。
そう考えるとLinuxが無難、じっくり自発的に使ってみたという意味で初めてだったのはArch Linux、*BSDと比べれば別によいけど、もう少し楽に扱える方がよい。。。となるとManjaro。。。
Mandriva、Mandrake系Mageiaもかなり気になる。。。
Linux Mintも気にはなるけど法的な話からコーデックなし版しか使えないんじゃ意味ない。
Fedora、Debianは、既にデスクトップマシンに入っているし。。。仮に候補にするにしてもFedoraは普段は良いが、基本、半年程度を目安になされるアップグレードは最新を追う為、致し方ないとはいえ結構手間がかかるからDebianか。。。
とりあえず、Debianの無線LAN検証をしていなかったのでやってみたら、Debian Jessieでは、数多くのドライバを提供してくれていて手持ちのUSB無線LANアダプタのチップ用ドライバもリポジトリからインストールでき、NetBSD/Fedoraで検証済みのwpa_supplicant.confもあったため、手間なく、簡単に使えることを確認できた。
仮想マシンにインストールしてみたことはあるものの、せっかくならまだ使ったことのないManjaroかMageiaか。。。ただArch LinuxベースのManjaroの場合、最新を追うという意味ではFedoraと同じようなことが起こり得るが、Archを使っていなくても重宝するほどArch Linuxのドキュメントは驚くほど充実している為、Fedoraよりは、安心して使えるか。。。
ダウンロードページを見ると。。。Manjaroは、コミュニティ版としてデスクトップ環境が一通りあるが、公式版としてはXFCE、KDE、Net-Editionがあり、最小限構成からの構築は厭わない一方、ダウンロード時に重くて時間がかかるのは勘弁。。。とNet-Editionをクリックしてみると570MB前後!?なんじゃそりゃ。。。ということで候補から外すことにした。
一方、Mageiaは、Classic Installation、Live Media、Network Installationの3択からいかにも軽量そうなNetwork Installationを選択するとFree Software CDとNonfree Firmware CDがあり、それぞれ、32bitと64bitを選択可、32bitを選ぶと前者が約31MB、後者が約47MBとニーズにマッチしたありがたすぎるサイズ。
ということでLinuxならMageia。
とは言っても*BSDも捨てがたく、というより、なんとなくなのだが、むしろ*BSDを使いたい。。。FreeBSDかOpenBSDか。。。FreeBSDを入れてみよう。。。
FreeBSD 10.1 RELEASEのインストールと10.3 RELEASEへのアップデート
USBメモリには、既にFreeBSD 10.1 RELEASEのインストーラがあるので10.3 RELEASE版がリリースされているものの、アップグレードの経験も兼ねて10.1をインストール。
FreeBSDのインストールは短時間で簡単、デフォルトでsudoはなかったものの、suはwheelグループに追加すれば使えるのでとりあえず、suで作業することに。
ところが、即アップグレードしようとしたら、超遅い。。。表示上もフリーズしたかのようで進捗がわかりにくいだけに追い討ちをかけて遅く感じる。。。xorgが入っていないからかCtrl+Cすら効かず、電源ボタン長押しで強制シャットダウンを繰り返したらアップグレードすらできなくなり、再インストールして試してみたりを繰り返すこと数回。
それでも使い勝手が良ければ、超遅いアップグレードにも目をつむることができるだろうと思い、FreeBSDインストール後、pkg installコマンドでパッケージをインストールしようとするとこれまた遅い。。。リポジトリの変更もできる模様も日本にはHTTP/FTP等のミラーサーバがないらしい。。。
日本ではPC-98ユーザー始め当時から日本に浸透していたことで有名なFreeBSDが、近年こんな状況とは、驚きを隠せず、予想外もいいところもFreeBSDにはご縁がなかったんだと諦め、NetBSD並みに軽快であるはずのOpenBSDにすることに。
OpenBSD 5.9インストール
OpenBSD 5.4のインストーラもUSBメモリに入っていたものの、こちらは、既に5.9がリリースされており、NetBSDのようにバージョンが違っても融通が利くことを期待して試してみたらダメだったので超軽量なネットワークインストーラcd59.isoをダウンロード。
OpenBSDはISOブートができるので既存のOpenBSDのGRUB2メニューを適宜書き換えてUSBブート、インストールはあっという間。
suもデフォルトで使えるし、5.8からsudoではなくdoasになったOpenBSD 5.9には、デフォルトでdoasが入っており、[permit nopass keepenv { ENV PS1 SSH_AUTH_SOCK } :wheel]と1行書いて/etc/doas.confを作成するだけでsudoと同様に使い始めることができた。
pkg_addでパッケージのインストールをしてみると軽いし、速い。
が、Totemは見る影もなく、Bansheeは一瞬見えるが即落ちクラッシュで起動しない。。。VLCは、2.2.1なのに[ユニバーサルプラグアンドプレイ]リンクがない。。。RhythmboxはGriloプラグインを有効にしてもJamendoは共有として表示されるも他マシンのOSやSharp AQUOS上では表示されているMiniDLNAやMediaTombが表示されない。。。
後述のようにMageiaを入れた際にどうやらVLCは、2.xのどのあたりからか、様々な理由から本体とプラグインを分けるようになった模様で[ユニバーサルプラグアンドプレイ]は、[vlc-plugin-upnp]とその依存パッケージを入れることで表示されることがわかった(が検出するのはまた別のパッケージのようである)ものの、OpenBSDには当該プラグインはなさそう?(MageiaとNetBSDを上書きインストールしたあとに気づいたから確認していませんが。。。)
代替策としてラズパイ上のSamba共有をマウントしようとしたら、mount -t smbfsでもcifsでもない。。。OpenBSDでは、昔からshlightコマンド(Sharity-Lightパッケージ)を使っていた模様。。。インストールしてやってみるもマウントできない。。。
ブラウザはFirefoxがお気に入りだが、特にJavaScriptを使ったページをタブで2つも開いたら、メモリリーク気味で実用に耐えないほど激遅。。。
近年のブラウザは機能豊富で相当重くはなっているのは確かも、RAMが512MBの時はNetBSD上でも似たようなものだったが、2GBに増強した今は、7〜8個タブを開いたところでそこそこ軽快であることからして何かが変。
仕方ないから「無理はしないでクラッシュ」設計なMidoriをインストール、そんなMidoriでもJavaScript多用のページ含め、タブを複数開いてもクラッシュすることもなく軽快そのもの、やはり、OpenBSD上のFirefoxの調子がいまいちの模様。
HTML5にシフトすべくFlashプラグインの行く末は長くはないものの、Flashプラグインが使えないらしきOpenBSD、とはいえ他のブラウザのプラグインすら使えるらしきChromiumのバイナリもあるということでプラグイン検証にとインストールしてみたら。。。これまた、何も表示されず起動しない。。。portsをmake installしてみたら、途中エラーで素直にインストールできなかった。。。
ちなみにChromiumとは直接関係ないが、NetBSDだとoption.mkがあってmake show-optionsで参照、/etc/mk.confで設定できるが、OpenBSDでは、オプションとかはどうやって設定するんだろう?ちょっと見た限り、ports内にはそういう仕組みはなさげに見える。。。
正規表現を使った複数ファイルの検索・置換(高度な検索・置換機能)にお世話になっているBluefish、また、geditは、と言ってもgeditについてはよくあることだが、OpenBSDに関してはscim-anthyと相性が悪いのか、他アプリではできる日本語入力ができず、ibus-anthyにしたらでき、他もこれで事足りた。
デスクトップ環境はどんな感じだろうとGNOMEとXfceをインストールしてみたらGNOMEは起動せず、Xfceは快調というべきか普通に使える。
そもそもOpenBSDではpkg_infoでリポジトリかインストール済みのバイナリパッケージを個別に検索できるものの、該当する複数のバイナリパッケージを検索するコマンドがない模様、ただ、pkgsrcでもできるが、portsをダウンロード、/usr以下に展開、/usr/portsに移動してmake search key(name)=keywordするという手はある。。。
NetBSDのpkg_infoはインストール済みパッケージのみ検索対象である一方、pkginでバイナリ、大元ならpkgse、ローカルならpkgfindやpkg_selectでpkgsrcの検索ほかができるのでmake searchしか使えないのは正直不便。
ならば、気分を変えて無線LAN。。。これまでDebian/Fedora/NetBSDで使えることを確認してきたUSB無線LANアダプタ、(OpenBSDのrun0を移植したらしいNetBSDではできているが、)OpenBSDではrun0がサポートしているとあり、確かにUSBポートに挿すと認識され、run0に関連付られるものの、設定してもIPアドレスの割り当てまでたどり着かない。。。
wpa_supplicantの-Dオプションの引数はopenbsdしかないようでwextやnl80211などだとエラーとなるからopenbsdでwpa_supplicant.confはctrl_interface_group以外は、他のディストロと全く同じ、ifconfig run0 downで停止、ifconfig run0 nwid SSID wpapsk PASSPHRASEなどとしてみても、dhclient run0としても。。。起動時にオプションを足したりしてみてもマシンを再起動してみてもno link......sleep。。。
ほとんどと言っていいほど使わないけどCUPSプリンタ。。。何もしなくても認識されていたりする。。。なんてことは、あり得なかった。。。
ざっと試してみたところ、OpenBSDは、FileZillaやVNCは普通に使えるのでテキスト編集、ファイルをまたいだ正規表現も使える検索・置換、FTP、ローカルファイルやCD/DVDデバイスのオーディオ視聴、VNCの利用程度ならデスクトップ用途としても使えなくもないかなという印象。。。
ただ、これだとNetBSD以上にデスクトップ用途には向いているとは言い難く、むしろNetBSDの方が、よっぽど使えるものが多く、課題は少なく、使い勝手もよいので入れ替えた意味がない。。。
MageiaかNetBSDか。。。
となれば、Mageiaか。。。発祥がフランスということもあってか、ちょっと見たところ英語のドキュメントも豊富とは言えなさそうも調べれば調べるほど魅力的なMageia。。。
Mageiaいいよな。。。でも*BSDって普段使いにしておかないと使わなくなってしまいそうで。。。それはそれでもったいない気がする。。。
Mageiaは、ノートじゃなくてデスクトップに入れようかな。。。(MageiaのベースにあるMandriva/Mandrakeの先祖がRed Hat Linuxで扱うパッケージもRPMでrpmコマンドもあるし、Debianユーザーも抵抗なく使えるようにか、apt-getやこれを模したapt-mga、なんならalienもあるが、)Debian/Fedora/NetBSDとはパッケージマネージャ(rpmdrake/urpmi)も違うから、練習しておくっていう意味でも。。。
とにかくインストーラをダウンロードしてインストーラ兼レスキュー用のUSBメモリに入れよう。。。
あ、NetBSDでgpt、待てよ?7.0からgptが使えるようになっているはず。。。と調べてみると完全対応ではない模様で条件付きもその名も直球ど真ん中gptコマンドとdkctlコマンドで参照、/dev/dk?を介してマウントはできるようになっていた。
その条件にひっかかってGPT/GRUB2を使ったUSBメモリにおいてgrub.cfgの編集しかできなかったが、NetBSDからアクセスできただけで以後の期待も膨らむというもの。
isoブートできたら楽だな。。。とLinuxマシンでMageiaのisoファイルをコピー、起動してみると、あっさりisoブートできた。。。最初はシェルベースだがロケール選択時からグラフィカルインストーラに引き継がれ、そのまま、デスクトップ環境もCinammon、MATE、GNOME、KDE、Xfce、LXDE、LXQTプラスアルファとなんなら全部インストールすることもできるなど、軽くて速くて美味いMageiaにますます惹かれていく。。。
なんてことをしていたら、Mageiaに惹かれる一方で、gptパーティションもマウントできるようになったのか。。。奇しくもいろいろ勘案するとFreeBSDやOpenBSDより安定していることもわかったし、いろいろあってもNetBSD、やっぱりおもしろいな。。。と思えてきた。
NetBSD 7.0のインストール
というわけで。。。ノートであるdynabookには、結局、NetBSD 7.0をインストールすることに。
FreeBSDやOpenBSDにも一定の期待を持っていただけに少し残念な結果になりましたが、以後、改善されることを祈りつつ、本来推奨されるほどではないNetBSD 6.1.5から7.0へのメジャーバージョンアップグレードをしてたけど大丈夫だったのか、少しばかり気にはなっていたので今回クリーンインストールできたということで、めでたし、めでたし!?
ちなみに今回、USBメモリに入れてあるNetBSD 6.1.2のインストーラでも使えるので、そのまま、NetBSD 7.0のリポジトリを指定してインストールしましたが、こうした小さな点も改めてありがたいと思いましたし、*BSDの中でもNetBSDが最も軽量で、安定し、OS自体のインストール、アップグレード、パッケージ管理など全般に渡ってスムースに運用でき、使用・運用するにあたって必要な情報もこれでも比較的豊富だったんだということがわかるに至りました。
NetBSDでもGNOME(GNOME2)やLibreOffice 5、Firefox 45(最新・最新に限りなく近い版)もバイナリのインストールだけで事足りるようになり、デスクトップ環境を整えるのもより楽になっていて快適。
後日、pkgin fugしたら、Firefoxも速攻で46.0にアップグレードされ、言語パックはないけど、もしかして。。。とLanguageから前バージョンのJapaneseのリンクをクリック、Mozillaの最新の46.0の言語パックのページに移動、[追加]ボタンをクリックしたら反映されました。。。おお、最初からこうしてくれればよかったのに。。。今度から(前から?)Firefox更新したら、言語対応はこうすればよいわけですね、楽ちん。
少し戸惑ったのが、IBusとSCIMでの日本語入力、これまでも何度も通ってきた道ですが、今回は微妙に違っていました。
まず、少なくともNetBSD(前述のインストールでOpenBSDでも)geditはscim-anthyでは日本語入力ができないので、これまでは、scim-anthyを使える(NetBSDでは未だwipにしかない)Plumaなどで代替してきた。。。というかgeditのルックスが変わってから馴染めないため、むしろ積極的にPlumaを使ってきましたが、今回、他NetBSDマシン上でpkg_tarup(インストール済みパッケージのバイナリを生成するNetBSDのコマンド)で生成したバイナリをインストールしても起動できず、原因もわからないという状況に初めて遭遇。
ibusならgeditでも日本語入力できることは以前やってみて知っていたのでそうしたのですが、今度は、Firefoxで日本語入力できなくなったことに気づきました。
メニュー、もしくはステータスバー?上のパネルにある言語変換ツールアイコンを右クリックすると開く[IBusの設定]でIBusの日本語ユーティリティーを確認するとデフォルトでは、AnthyとJapaneseという日本語ユーティリティーが有効となっていましたが、mozcならいけるのでは?と根拠なく思い、ibus-mozcをインストール(mozc-utilsも依存関係として自動インストール)したものの、やはり、Firefoxで日本語入力できない。。。ところがダメ元で試してみた同じMozillaファミリーのSeamonkeyでは日本語入力できる。。。なんで?
「firefox ibus」をキーに検索したところgihyo.jp 第274回 Fcitxを使用するがあり、肝心な表題を見落としつつ、技評なら。。。とざっと流し読みしたら2ページ構成の1ページめだけ読む限り、ibusとscimの話だけで終始しているように見えた、その時、ページ内検索したらコメント欄にFcitxを入れたらFirefoxで日本語入力できるようになったとあり、あぁ、Fcitxね、使ったことはあるけどNetBSDのバイナリにはないよね。。。?と思ったら。。。fcitxとscim-fcitxがあったので入れてみました。
最初は、scim-fcitxが起動するかな?とscimを起動させてみましたが、geditはやはり日本語入力できず、Firefoxはそもそもscim-anthyだけでも機能していたので状況は変わらず。
ということは、ibus起動時にfcitxがあると日本語入力できるようになるのか?とやってみたら、見事にFirefoxでも(fcitxがなくてもibusなら日本語入力できたgeditも当然ながら)日本語入力できるようになりました。
尚、環境は、NetBSD 7.0、GNOME 2.32.1、ibus-1.5.13、ibus-anthy-1.5.6、scim-fcitx-3.1.1nb21、anthy-9100h、kasumi-2.5nb20、scim-anthy-1.2.7nb22、gedit-3.16.4、firefox-45.0.1。
が、このようにバージョンを調べるにあたり、後で気づいたのですが、fcitxの方はなぜかインストールされておらず、scim-fcitxのインストールだけでibusでも機能し、Firefoxでも日本語入力できるようになった模様。。。これはこれでなんで?そういうもの?
NetBSD 7.0で謎の無線LAN途中切断が頻発
が、数日使っていたら、無線LANが起動時につながらず、/etc/rc.d/network restartしてもダメでマシンを再起動したりといろいろやってようやくつながったり、/etc/rc.d/network restartでつながったものの、スリープしたわけでもないのに突如、無線接続が切断されたり、同じNetBSD 7.0でも以前は全くなかった状況が、なぜか、頻発するようになりました。
無線だけに周囲の利用状況から混雑しているという可能性もなくもありませんが、普段使いするようになってからは、こんなことに遭遇したことはなく、しかもNetBSD、FreeBSD、OpenBSDからのNetBSDのクリーンインストールは1〜2日の出来事であり、昨日の今日で突然状況が変わるというのは考えにくい。。。
他に違いといえば、NetBSDを6.1.5から7.0にアップグレードしたか、7.0をクリーンインストールしたかくらいしか、あ、100均のUSBハブにドングル接続しているって言ってもdynabookに直接つなげても同じだし。。。気づけば使用中のUSB無線LANアダプタBUFFALO WLI-UC-GNM2は、スペック的に同等の他製品よりも消費電力が高い傾向にあり、これは購入前からわかっていたことですが、ネット情報では熱暴走も囁かれていたものだけに、やっぱり熱でやられたかな。。。1000円前後で買って半年、妥当なのかどうかもわかりませんが、価格帯は同じくらいにしても今度は、消費電力の低いものを選ぼうかと。
MageiaとNetBSDをマルチブート
直接NetBSDとは関係ないアクシデントですが、このタイミングってMageiaを入れてみなっていうサインかな?なんて意味として受け止めてみることにしてインストーラも仕込んで経過も確認したことだし、Mageiaをインストール。
ただ、NetBSDも捨てがたい(とは言っても他のデスクトップ2台にも入っているけど普段使いのノートにも入れておきたい)からHDDは80GBだけどNASもあってマシン自体にそんなに容量要らないからNetBSDとMageiaをマルチブートすることに。
一応、縮小対応のFFSv1にしたからできなくもなさげも小難しそうなのでNetBSDも入れ直すことにし、インストーラ任せだとどんなパーティション操作ソフトが入っているのか、使いやすいのか定かではないのでインストーラ兼レスキューUSBメモリに入れてあるGPartedでGRUB2、NetBSD、Mageiaの3つにパーティションを分割してそれぞれインストール。
バックアップ
尚、ラズパイをサーバとして2TBの外付けHDDをNASとして使っていますが、なぜか、PlumaやBluefishでNAS上のファイル直接扱おうとするとおかしなことになる為、ローカルに置いてrsyncでバックアップしています。
ただ、そうなるとクライアントが多い場合、ローカルをどこにするか、現状、PavilionにDebian/Fedora/NetBSD、e-oneにNetBSD、dynabookにMageia/NetBSDという状況、都度コピーしたり、マウントして作業したりしてもよいのですが、基本的にバックアップを要するような編集作業はメインとして使うことにしたdynabookのみで、よってMageiaかNetBSDで行ない運用することにしました。
但し、LinuxからNetBSDは、読み取り専用でしかマウントできない、一方、NetBSDからは、ext2/ext3ならext2fsでLinuxをマウントできるという現状があります。
よってLinuxとNetBSDをマルチブートする際には、Linux側をext3でフォーマットの上、インストール、NetBSDから読み書きできる状態でLinuxを、Linuxから読み取り専用でNetBSDを自動マウントするようにしており、今回もMageiaをローカルに、NetBSDからはMageiaのパーティションを読み書きモードでマウント、どちらからでも編集、rsyncでバックアップできるように運用しています。
ちなみにhow to mount ffs partition under linux何れも有効なオプションではあるものの、ファイルシステムFFSv1とFFSv2で異なるのか、FreeBSDと認識されたのか、理由はわからないのですが、MageiaからFFSv2としたNetBSDをマウントする際、オプションとして[ufstype=ufs2]を渡す必要がありましたが、DebianやFedoraからFFSv1としたNetBSDをマウントする際のオプションは[ufstype=44bsd]なんですよね、何が違うんだろ?やっぱり、FFSv1/FFSv2の違いかな?
というわけで今回は、NetBSDはさておき、仮想マシンにインストールしたことはあるものの、実際に使用するのは初めてなMandriva、Mandrake由来のMageiaをレビュー。
関連リンク
- PC/Personal Computer・パソコン
- 古いパソコンの再利用
- OS入れ替えdynabook Satellite T30 160C/5Wインデックス
- dynabook Satellite T30 160C/5Wの主な仕様と状態
- dynabook Satellite T30 160C/5Wの使用用途とOS選定
- dynabook Satellite T30 160C/5W、その結果は・・・
- dynabook Satellite T30 160C/5W RAM増強とHDD換装を検討
- dynabook Satellite T30 160C/5W RAM増強と動画ストリーミング再生
- dynabook Satellite T30 160C/5W HDDの換装を検討
- dynabook Satellite T30 160C/5W HDDをSSDにクローニング・換装
- dynabook Satellite T30 160C/5W Clonezillaでクローニング
- dynabook Satellite T30 160C/5W HDDをSSDに換装
- dynabook Satellite T30 160C/5W 初SSDの感想
- dynabook Satellite T30 160C/5W NetBSDからFreeBSDのちOpenBSDチラッとMageia結局NetBSDとMageiaをマルチブート
- dynabook Satellite T30 160C/5W Mageiaをレビュー
- dynabook Satellite T30 160C/5W NIC不調とUSB有線/無線LANアダプタ
- dynabook Satellite T30 160C/5W NetBSDリポジトリに収録されたLXDE/MATEを追加インストール
- dynabook Satellite T30 160C/5W オーディオ・サウンドカードとUSBサウンドアダプタ
- dynabook Satellite T30 160C/5W Debian 8.4.0 Jessieをインストール
- dynabook Satellite T30 160C/5W 接触不良により充電器・ACアダプタを購入
- dynabook Satellite T30 160C/5Wを分解・掃除
- dynabook Satellite T30 160C 5W いよいよ限界!?
- Raspberry Pi 3 Model B+とノートPC液晶他でパソコン化